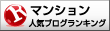【国勢調査2025】調査員の仕事に疑問!マンションのオートロック!

2025年9月20日(土)、国勢調査の調査票を調査員から直接受け取りました。ちょうど、エントランスのオートロック操作盤で調査員にバッタリ会ったので、手渡しで受け取りました。
国勢調査の重要性は理解していますし、ニュース等で協力を呼びかけていることも知っています。しかし、マンションにおける国勢調査の調査票の配布方法に疑問が残りました。
- 国勢調査:調査員の仕事に疑問!
5年に一度、日本に住むすべての人と世帯を対象に行われる国勢調査。
それは、少子高齢化対策、防災計画、地域のインフラ整備など、私たちの暮らしの根幹をなす政策を立案するための、極めて重要な基礎データとなります。
その重要性は十分に理解しているつもりです。しかし、先日、私が住むオートロック付きマンションのエントランスで国勢調査の調査員の方と遭遇した際、その調査方法に対して、いくつかの大きな疑問と時代との深刻なズレを感じずにはいられませんでした。
その方は、調査員証らしきものを首から下げ、インターホンパネルの前で熱心に各部屋を呼び出していました。
私がエントランスに入ると、「国勢調査の者です。お部屋番号を教えてください。」と声をかけられました。
部屋番号を告げると、該当の調査票を探して手渡されました。ただそれだけのことでしたが、この一連のやり取りの中に、現代社会が抱えるプライバシー意識、セキュリティ、そして効率性といった観点から、見過ごすことのできない問題点がいくつも潜んでいたのです。
この経験を通して感じた国勢調査の訪問調査における課題を、「本人確認の不在」「オートロックという壁」「時代に逆行するアナログ手法」、そして「調査員の高齢化と『昭和スタイル』の限界」という4つの視点から整理し、未来志向の調査のあり方について考えてみたいと思います。
■ 目次 ■
疑問点1:その調査員、本物ですか?

まず、最初に感じたのは、本人確認のあまりの杜撰さに対する不安でした。
調査員の方は、私が「このマンションの居住者である」という自己申告を信じ、部屋番号を尋ねるだけで、何ら身分を確認することなく調査票を渡してくれました。
もちろん、調査員証は携帯されていましたが、私自身がその調査員証を詳細に確認したわけではありません。
そして、もっと重要なのは、調査員側が私の本人確認を一切行わなかったという事実です。
本当に、マンションに住んでいる本人なのか?部屋番号があっているのかの確認が行われませんでした。
免許証やマイナンバーカードなどの身分証明書の提示も求められず、ただ口頭での確認でした。
近年、国勢調査を装った「かたり調査」が社会問題となっています。
これは、調査員になりすまして個人情報を不正に聞き出したり、金銭を要求したりする悪質な詐欺行為です。
総務省統計局も、不審な訪問や電話には注意するよう広く呼びかけています。 にもかかわらず、現場の運用は「調査員を名乗る人物」と「居住者を名乗る人物」が、互いに何の疑いも持たないという性善説に基づいているように見えました。
もし、私が悪意を持つ第三者で、たまたまそのマンションに出入りできる人間だったとしたらどうでしょう。
適当な部屋番号を告げれば、いとも簡単に調査票を手に入れられたかもしれません。
調査票には、世帯主の氏名や家族構成といったプライバシー情報が記載されている場合もあります。個人情報保護に対する社会の目が厳しくなる一方、国の最も重要な統計調査の入り口が、これほどまでに無防備で良いのでしょうか。
せめて、郵便受けの名前と照合する、あるいはオートロックの解錠をもって居住者とみなすなど、何らかの確認プロセスを設けるべきではないかと感じました。
疑問点2:エントランスの”主”と化す調査員
次に問題だと感じたのは、調査員の方がオートロックのインターホン操作盤を長時間にわたって占有していたことです。
私が遭遇した短い時間だけでも、その方は複数の部屋を呼び出していました。
おそらく、不在の部屋も含めて、一軒一軒応答があるまで呼び出しを続けていたのでしょう。
これは、他の居住者がインターホンを使いたいときに使えないという、直接的な迷惑行為につながります。
宅配業者や来客者が、エントランスで立ち往生してしまう可能性も十分に考えられます。
そもそも、オートロックシステムは、不審者の侵入を防ぎ、居住者のプライバシーと安全を守るために設置されています。
しかし、調査員がエントランス内で粘り強く居住者を呼び出すという行為は、このセキュリティシステムの思想と真っ向から対立します。
さらに問題なのは、こうした行為が、マンションのセキュリティを脆弱にする「共連れ(ともづれ)」を誘発しかねない点です。
インターホンの呼び出しに応じた居住者がエントランスの自動ドアを解錠したタイミングで、他の人間がすり抜けて侵入する。調査員自身にそのつもりがなくても、結果的に不審者の侵入を助長する危険性をはらんでいるのです。
現代の集合住宅、特に都市部においては、オートロックはもはや標準装備です。
この「壁」を前提としない、一軒家への戸別訪問を基本とした従来型の調査手法は、現代の居住形態に全く適合していないと言わざるを得ません。
居住者の協力なくしては中に入れないという現実を前に、インターホン前で粘るという非効率的で、かつ他の居住者に迷惑をかける方法しか取れない現状は、早急に見直されるべきです。
疑問点3:なぜ手渡しにこだわるのか?
そこで浮かんだのが、「なぜ、郵送ではダメなのか?」という素朴な疑問です。
【追記】住民票なしで、居住している人が把握できないから郵送はダメなんだと分かりました。訪問日時を事前に知らせて頂けると配布率も上がるかもしれませんね。
国勢調査では、インターネットによる回答が広く推奨されており、その利便性は年々向上しています。にもかかわらず、なぜ調査員はわざわざ各戸を訪問し、調査票を手渡しで配布することにこだわるのでしょうか。
私が遭遇した調査員の方は、目測で80歳前後と思われるご高齢の方でした。(これにも驚き!!)
長年の経験から、対面で趣旨を説明し、調査票を手渡すことが最も確実な方法だと信じていらっしゃるのかもしれません。また、高齢者など、インターネットの利用が困難な世帯への配慮という側面もあるでしょう。
しかし、全ての世帯に対して、このアナログな手法を適用するのは、あまりに非効率ではないでしょうか。
共働き世帯や単身世帯が増え、日中の在宅率が低い現代において、訪問調査は調査員と居住者の双方にとって大きな負担となります。
何度も再訪問を繰り返す調査員の労力は計り知れませんし、居住者にとっては、いつ来るかわからない調査員を待ち構えるストレスや、在宅時に対応する煩わしさがあります。
原則として全世帯に調査票を郵送し、オンライン回答を第一の選択肢とする。
そして、オンラインでの回答がなかった世帯や、郵送した調査票が返送されない世帯、あるいは支援が必要な世帯に対してのみ、訪問調査を行うという段階的なアプローチは取れないのでしょうか。
デジタル化の恩恵を最大限に活用し、訪問調査を「最後の手段」と位置づけることで、調査の効率性は飛躍的に向上し、多くの問題は解決に向かうはずです。
マンションの理事長に、全住戸の調査票の配布を依頼する等の対応が出来ても良いのではないかと考えます。または、理事長と同行して協力を求めるなどの方法もあるのではないかと考えます。
まとめ:信頼される調査であり続けるために
今回の経験を通して、私が目の当たりにしたのは、国の重要な基幹統計調査が、いまだに「昭和の時代」の価値観や手法に大きく依存しているという現実でした。
それは、調査員の善意と、驚異的なまでの忍耐力によって、かろうじて成り立っている極めて脆弱なシステムです。
お会いした調査員の方個人を非難するつもりは毛頭ありません。
むしろ、高齢にもかかわらず、国の重要な任務を担おうとするその真摯な姿勢には、頭が下がる思いです。しかし、問題は、その善意に甘え、時代に合わせたシステムのアップデートを怠ってきた国全体の仕組みにあるのではないでしょうか。
プライバシーやセキュリティに対する国民の意識は、この数十年で劇的に変化しました。住まいの形態も、地域社会との関わり方も、大きく様変わりしています。
国勢調査が、これからも国民から信頼され、正確なデータ収集という本来の目的を果たしていくためには、こうした社会の変化に真摯に向き合い、調査方法そのものを抜本的に見直す時期に来ています。
オンライン回答のさらなる推進とUX(ユーザーエクスペリエンス)の向上、郵送方式の原則化、そして訪問調査の役割の再定義。
これらを組み合わせ、テクノロジーと人の力を最適に配分することで、より安全で、効率的で、そして現代の暮らしに寄り添った国勢調査の姿が見えてくるはずです。
5年後、次の国勢調査が行われるときには、エントランスで調査員が立ち往生するような光景が、過去のものとなっていることを切に願います。
この記事に関連する記事一覧
この記事を書いた人
独身でマンションを購入し、売却を経験した管理人です。失敗や後悔をすることがないように経験から得られた知識を発信することでマンション購入のお役立ちとなるように願っています。「マンションは管理を買え!」と言われるように、購入して後悔のないように願うばかりです。理事長や副理事長の経験もあり、管理委託費の削減も行いました。







 ←ダウンロード可能なブログ記事です。自由に
←ダウンロード可能なブログ記事です。自由に